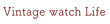ホイヤーが生み出した無敵クロノグラフ『オータヴィア』Ref.7863Cの構造と魅力解説
こんにちは、ヴィンテージウォッチライフの妹尾です😊
本日の動画では『ホイヤーが生み出した無敵クロノグラフ『オータヴィア』Ref.7863Cの構造と魅力解説』という内容で解説して参ります。
マジでかっこいいし、希少性の高いモデルですので動画を見終わった頃には、多分欲しくなってると思いますので、是非とも最後までお付き合いくださいませ。
ホイヤー製『オータヴィア』Ref.7863Cとはどんな時計?
ホイヤーのRef.7863Cは、1968年から1971年頃にかけて製造されたオータヴィア(Autavia)シリーズの中でも、特に魅力的なヴィンテージ・クロノグラフのひとつです。
2カウンターの手巻きクロノグラフでありながら、日付表示を備えた"Dato(ダート)"モデルである点や、特徴的なケース構造、そして現存数の少なさから、現在ではコレクターズアイテムとして高い評価を受けています。
既にご存知の方も多いと思われますが、まずはオータヴィアとは何なのか?
ということについて解説します。
オータヴィアとは?
まずオータヴィア(Autavia)とは、"AUTomobile(自動車)"と"AVIAtion(航空)"を組み合わせたホイヤー独自の造語で、もともとは1930年代に航空機用のダッシュボードタイマーとして誕生しました。
腕時計としてのオータヴィアは1962年にリリースされ、モータースポーツに特化した実用クロノグラフとして人気を博しました。
スティーブ・マックイーンに代表されるモナコとは異なり、オータヴィアは実際のレーシングドライバーたちが使用していた"リアルツールウォッチ"なのです。
では次に、この個体の素晴らしいポイントであるゴーストベゼルについて解説します。
特別なゴーストベゼルについて
Ref.7863Cにはさまざまなタイプの回転ベゼルが存在しますが、中でも特に人気が高いのが"ゴーストベゼル"と呼ばれる、経年変化によって黒からグレー、別の言い方では浅いネイビー色に褪色したベゼルです。
本来はブラックだったベゼルが紫外線や湿気、経年使用により褪色したものであり、これが個体ごとに異なる表情を生むため、ヴィンテージファンの間では高く評価されています。
皆様ご存知の通り、全ての個体でゴーストになるわけではありません。
特定のロットで製造された一部のモデルだけが、経年によってゴーストに成りうるのですが、ゴーストになる個体の方が圧倒的に少ないのが現状であると言えるでしょう。
黒のベゼルもめっちゃかっこいいんですが、ゴーストの魅力ってそもそもがこんな色のベゼルの腕時計を誰もが着用してないってことですよね!
そしてこの色味もかっこいいじゃないですか・・・・
シルバーのステンレスのケース、淡いブルーのベゼル、文字盤のブラックと黄金比率の配色ですから、男性であればこれをかっこいいと思わない人はまずいないと思いますね。
では次に、気になるムーブメントを見てみましょう。
ムーブメントについて
ではこちらの画像をご覧ください。

Ref.7863Cに搭載されているのは、手巻き式のValjoux社製Cal.7732ムーブメントです。
こちらも皆様ご存知だと思われますが、このベースムーブメントはCal.7730でありこのムーブメントにデイト表示を追加させたのがCal.7732でございます。
デイトが入る場所は、文字盤から見た時の6時位置ですね。
最近公開した動画では、こちらのハミルトンはCal.7730が搭載されていたモデルなので、気になる方はこちらの動画もご覧ください⬇️
カム式の採用ではありますが、そもそも現代においては手巻きのクロノグラフであること自体に価値があります。
さらには、クロノグラフの名門であり、バルジュー社が手掛けているクロノグラフムーブメントというのは、安心感がありますよね。
レマニアのムーブメントCal.5100もそうなのですが、Valjoux 7730系は信頼性が高く、整備性にも優れており、街の時計屋さんで修理して貰えることも魅力のポイントだと言えますよね。
ちなみにこちらも皆様ご存知でしょうが、バルジューCal.7730は元々はヴィーナス社製Cal.188をベースに改造されたムーブメントです。
ヴィーナスってのは、最初の頃のナビタイマーの9割に搭載されていたクロノグラフムーブメント製造メーカーですね。
30分積算計を備えた2レジスター仕様で、振動数は18,000振動。
ムーブメントブリッジには"HEUER LEONIDAS S.A."の刻印があり、ホイヤーとレオニダス社の統合後であることを示しています。
レオニダスについて、のちのパートで詳しく解説しますね。
そんな素晴らしいムーブメントを搭載してるオータヴィアですが、ケースもこれまた一級品で作り込まれていますので、そこも一緒に見ていきましょう。
ケース構造について
ではこちらの画像をご覧ください⬇️

Ref.7863Cの魅力のひとつが、そのケース構造です。
これはマジで凄いですよ!
ケースはスナップバック式でありながら、防水性を意識した"コンプレッサースタイル"が採用されています。
画像をしっかりご覧頂きたいんですが、パッキンの内側にムーブを収納するインサートが見えると思いますが、その内側に6箇所突起が出ているのが分かると思います。
これはガスケットなんですね。
構造は、通常時はケース自体にわずかな弾力を持たせ、水圧がかかると裏蓋がガスケットを押し込み、裏蓋とパッキンが密着して気密性が高まるという構造です。
結果として、ねじ込み式ではないにもかかわらず、ある程度の防水性能が確保されていました。
この構造を初めて世に生み出したのは、EPSA社であり大半が防水を確保する際にはEPSA社のケースを使っていました。
今回のホイヤーはEPSA社製のケースを採用しておらず、どうやら自社でこれを作っているみたいです。
完全なEPSA社製コンプレッサーケースではないものの、その影響を受けた設計思想が色濃く反映されています。
EPSA社のケースをご存知でない方は、こちらの動画で詳しく解説しておりますのできににある方はご覧ください⬇️
では次にヴィンテージホイヤーを見ていくと必ず出てくる『レオニダス』という会社についても見ていきましょう。
レオニダス『LEONIDAS』とホイヤー『HEUER』の関係
ヴィンテージホイヤーの時計を見ていくと、まぁまぁの確率でレオニダスという会社が出てきます。
そして、基本的にはホイヤーレオニダスという刻印が打たれています。
まずこの解説でしが、ムーブメントや裏蓋に刻印されている"HEUER-LEONIDAS S.A."は、1964年にホイヤーがレオニダス社と合併して誕生した社名です。
レオニダスは19世紀から続くスイスの時計メーカーで、軍用クロノグラフなどを多く手がけていました。
レオニダス社は別にムーブメントを作れるわけではなく、他の会社と同様にバルジューやETAからムーブメントを購入して、自社の時計に乗せていました。
となると、ホイヤーが買収するメリットなんてないように感じられますが、レオニダスには実績があったんですね。
レオニダスは第二次世界大戦以降、スイス陸軍、ドイツ空軍、イタリア空軍、フランス軍など多くの軍隊にクロノグラフを納入していました。
特にドイツ軍へのクロノグラフは、信頼性の高さで知られていました。
軍にも採用されるクロノグラフですからね。
エボーシュであっても、高度な完成品に持っていく技術は相当なものだったんでしょうね。
よってホイヤーは当時、軍事市場への参入が弱かったため、レオニダスの販売ルート・信頼・製品群をそのまま取り込めるのは大きな利点となったのです。
このように、軍需の強化としてレオニダスを買収したのですが、結果的にその後に続いていくこととなるモータースポーツの分野でホイヤーは頭角を表すことになるので、ここでもレオニダスのクロノグラフの技術は生かされたのでした。
この合併により、ホイヤーは技術力と製品ラインナップを拡充し、モータースポーツに特化したクロノグラフ開発をさらに推進することができたのです。
Ref.7863Cは、約3年という短い期間のみ製造されたモデルであり、市場に出回る数は限られています。
オータヴィアで6時位置にデイトが入ったモデルを見かけないのは、そういった理由があるからなんですね。
Ref.7863Cは、見た目のカッコよさだけでなく、設計思想や歴史的背景、構造のユニークさまで含めて“語れる時計”です。
ヴィンテージホイヤーの中でも、実用性と個性、そして高い完成度を兼ね備えたこのモデルは、まさに知る人ぞ知る、隠れた名品と言えるでしょう。